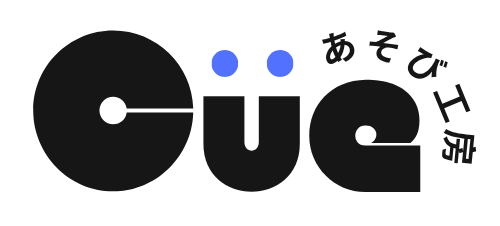ワークショップを検討されている方へ
まずは子ども達の現状を客観的にみてください。
いきなり、まとめます。
子どもの数は44年連続で減少しているのに、不登校児童は11年前の3倍(34.6万人)に増加。
将来に夢や希望がもてず、挑戦もしたくない。
自分には誇れる個性がなく。他人からも必要とされていないと思っている。
若い世代の死因トップはすべて自殺。
少しデータを載せます。
文科省のデータでは2023年度、不登校の小中学生は34万6482人で11年連続増加。
2012年度の不登校児童は11万2,689人なので、約3倍に増加。
一方、子どもの数は減っています。
総務省のデータでは
2025年4月1日時点で外国人を含む15歳未満の子どもの数が昨年より35万人少ない1366万人(44年連続減少)
17~19歳の若者1000人への調査(2022年と2024年データ)
「日本財団『18歳意識調査』調べ」
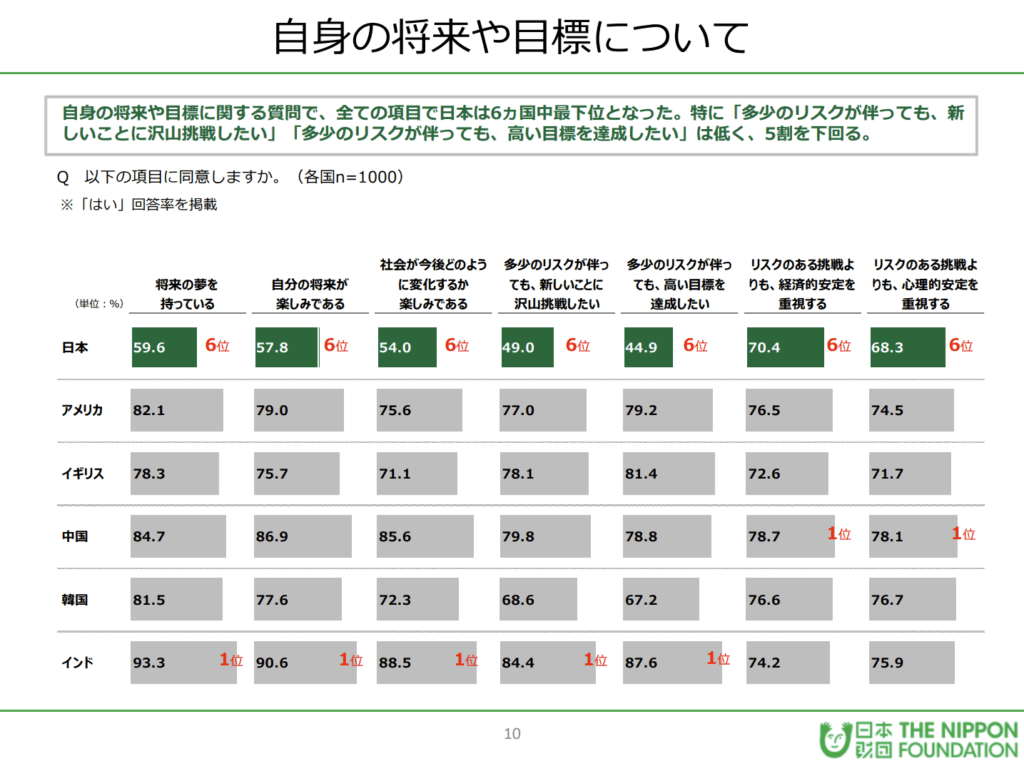
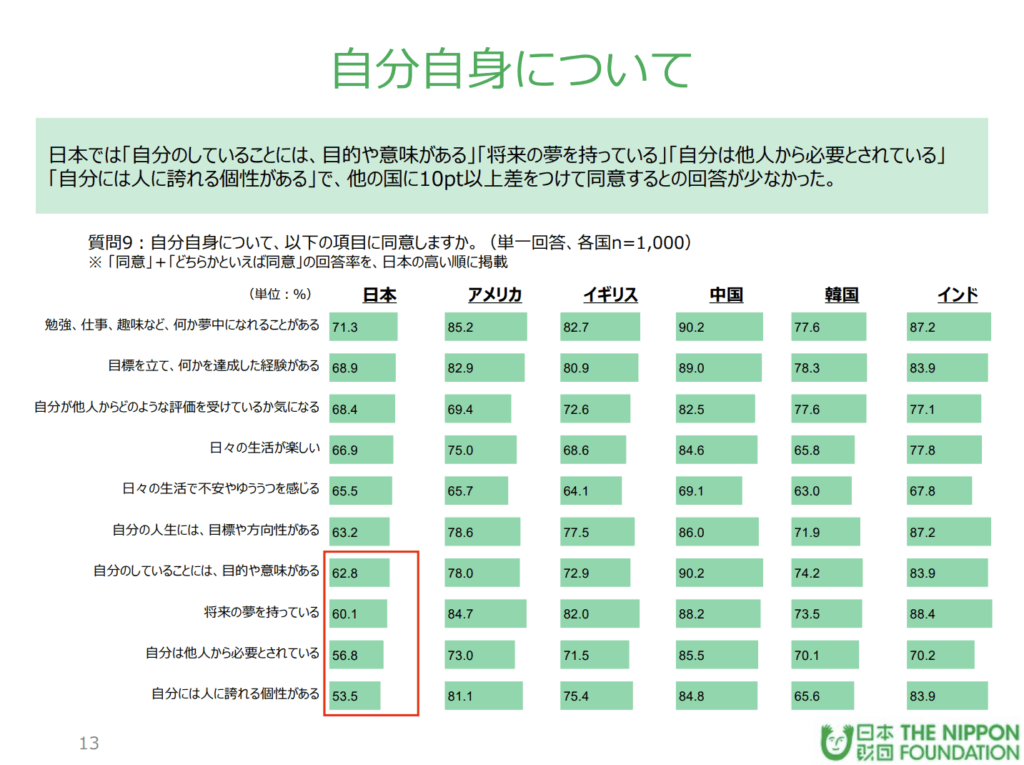
厚労省のデータでは、
2021年度日本人10~39歳のすべての年代の死因1位は自殺
G7各国と比べて自殺率が最も高く、10~19歳の死因、自殺1位は日本だけです。
2024年、小中高生の自殺は529人と毎日誰かが亡くなっています。
どうでしょうか?
自分の周りの子ども達は元気に育っているかもしれませんが、客観的事実はこうです。
日本の子ども達は昔より確実に生きづらいんです。
その生きづらさはどこからくるのか?
その原因の一つは、
「正解を覚える教育」
にあると考えています。
一問一答で正解と間違いに分けられ、周りの人から評価され続けると、物事には正解と間違いがあるという世界観が刷り込まれる。
そうすると、たくさん正解を知りたいし、人にも教えてあげたい。
そして、間違いはなるべく避けたいと思うのは自然なこと。
このあと、物事には正解と間違いがあるという世界観がもたらす問題を、少し大げさに言いますがご容赦ください。
自分の感情<正解
自分の考えはだいたい却下される。我慢するほど褒められる、感情の抑圧。
そのうち、感情が希薄になり、自分の考えもわからなくなる。
自分の評価<他人の評価
とうい状態になる。
いくら頑張っても、必ず上位の存在がいるので、自己嫌悪になる。
間違えてはいけないという心理が働くので、チャレンジができない。
正解は調べるので、経験は重視しない。正解が欲しいだけなので推論や類推もあまりしない。一つ聞いても一つしか分からない。少し考えたらわかる嘘にも騙される。これが当たり前だからと言われたら、従ってしまう。
コミュニケーションにおいても
間違えていると思った人の意見を聞けない。人をラベルで判断しがち。
善意から、他人を正解に誘導したい。例:子どもをコントロールする親。
など
物事には正解と間違いがあるという世界観が強いと(場合によっては正義と悪)
そういう傾向があるのでは?経験と知識に基づいて、自分で考えたわけです。
子ども達は、家族や学校、近く友人など、限られた狭い世界で生きています。
大人にとっては些細なことでも、子どもにとっては耐え難いことがあります。
仮に、正解にがんじがらめされた世界で自己嫌悪になりながら、生きづらさを感じている子ともがいたらどうでしょう?
ほとんどの場合、自力では抜け出せません。
周りの人間が気づいて、助けてくれたら良いのですが、それは運です。
自力で、がんじがらめの世界から抜け出すには、自分で考える力が必要です。
シリアスな話はここまでにして、
ここからは遊びの話です。
我々が子どもにできることは「自分で考える」ことをサポートする。
それを最もクリエイティブな状態である、遊びから提供します。
ここで必要とされている「自分で考える力」って具体的にはなにか?
がんじがらめの世界から抜け出すのに必要なのは
「みる力」
ものの見方、新しい視点を獲得する力です。新しい視点は普通、体験によって獲得できます。
例えば、お笑い芸人は「お笑いの視点」を持っているので、失敗や理不尽に遭遇したら、ネタになるのでラッキーと思えます。
外国に住めば、日本の常識は通用しないことがわかります。常識の権力は弱まり、新たな視点が獲得できます。
わかりやすいので例に挙げましたが、お笑い芸人になったり海外留学しなくても新たな視点を獲得し、世界を広げることができます。
他人の視点から学ぶことです。
その一つの方法として
「対話型鑑賞」があります。
詳細は省きますが、一言でいうと
アート作品をみて、他者の意見をきく。
アートは正解がないので、さまざまな意見がでます。
その視点から学ぶ方法です。
他にも、演技が効果的です。
役になりきることで普段の自分とは違う景色が見えます。
そうやって新しい視点をどんどん獲得することで、視野が広がり視座も高くなり、世界が広がります。
そして伝えるこのと難しいところは、
この文章を読んで、「なるほど、新しい視点の獲得ですね。実践してみます!助かりました!」とはならないところですね(笑)
そのためのワークショップです。
ワークショップで、体験し実感することが必要です。
「自分の力で現実の認識を変えられる」という体験をします。
子ども達は、運よく色んな体験ができても、自力では体験の機会は得られません。周りの大人がその主導権を握っています。
いろんなものの見方を獲得し、一人一人違う自分の世界を、ご機嫌チューニングにアップデートするきっかけになればと願っています。
最後に、
社会性を否定しているわけではありません。快適に生活する為に、社会性も重要。社会性は知っていれば便利なもので、自分を縛るものではないという認識です。
「空気を読む」に似ています。空気は読めた方が便利だが、空気に従うかどうかは自分で決めれば良いと思います。
競争も目の敵にされがちですが、遊びの重要な要素。
スポーツのエンターテイメント性は競争なくして語れません。
競争は人間の優劣を競うものではなく、エンタメ性だと教えてあげれば良いと思います。
そもそも「これが良くて、これが悪い」のような二元論的考えは、正解と間違いでできた世界観と相性がよいのかもしれません。
「楽しいはつくれる!」
是非一度、ワークショップに呼んでください!